
自治体が仕掛けるイノベーション最前線 #CEATEC 2025

CEATEC 2025で開催された「テクノロジーが切り拓く地域産業:自治体協業ニーズピッチ&イノベーション討論会」で、4つの自治体が先進的な取り組みを披露した。
仙台市のナノテラス活用から群馬県の海外スタートアップ連携まで、地域課題解決に挑む職員たちの変化と挑戦を共有する。
自治体のイノベーション戦略

トップバッターとして登壇した仙台市経済局イノベーション推進部首都圏プロモーション担当係長の今井大二郎氏は、東北唯一の政令指定都市としての強みを強調する。
「東京駅から新幹線で90分で行ける場所です。意外と近い東北を感じていただければと思います」(今井氏)。
同市の最大の武器は、今年稼働を開始した巨大放射光施設「ナノテラス」だ。仙台駅から地下鉄でわずか9分の東北大学青葉山キャンパス内に設置されたこの施設は、「巨大な顕微鏡」として様々な産業での活用が期待されている。
実際、地元企業のアイリスオーヤマは食品・米飯分野での放射光解析やX線・CT観察などにナノテラスを活用しており、製品開発・評価への応用が進んでいる。
同時に仙台市は都心再構築プロジェクトを推進中だ。
8月には初のグローバルスタートアップカンファレンス「DATERISE!」を開催し、延べ1,700名が参加した(市発表では会場626名、オンライン948名、関連イベント含めると2,360名)。
続いて群馬県産業経済部未来投資・デジタル産業課スタートアップ推進室チームリーダーの穗坂一浩氏は、県の産業構造転換への取り組みを説明した。
「群馬県というと草津温泉や伊香保温泉、キャベツやネギといった観光や農業のイメージが強いと思いますが、実は一番多いのは製造業です」(穗坂氏)。
スバルの国内唯一の本社工場を擁し、製造業のピラミッド構造が形成されている群馬県だが、産業構造の転換と労働人口減少が課題となっている。
同県はこれらの課題解決に向け、既存産業とスタートアップの新しいテクノロジーを組み合わせる戦略を採用している。
特筆すべきは海外スタートアップとの連携プログラムだ。
欧州のイノベーション機関 EIT(European Institute of Innovation and Technology:欧州イノベーション・技術機構)と連携し、群馬県企業と海外スタートアップのマッチングを推進している。
塩尻市商工観光部先端産業振興室室長の太田幸一氏は、職員のスキル向上について具体例を交えて説明した。
「自動運転を始めようと思った時に、レベルの違いすら分からなかったのが現状でした。リテラシーをどうつけるかというと、座学はもちろん大事ですが、やはり一緒にプロジェクトを企業の皆さんと協働していくことで得られるものが大きいですね」(太田氏)。
静岡市経済局商工部産業政策課主任主事の鶴田佳代氏は、同市のスタートアップ支援事業が3年目を迎え、予算を10倍に増やして本格展開していることを報告した。
「静岡市としては今3年目で、予算も10倍に増やして、積極的に取り組んでいるところです。ぜひいろんな皆様と協業・協働しながら事業をつくっていきたいと思います」(鶴田氏)。
変わる自治体職員

地域イノベーションを支える最も重要な変化は職員自身にある。従来の行政職員のイメージを覆すような、スキル向上と意識改革が各地で進んでいる。
塩尻市の事例は特に象徴的だ。同市の自動運転担当者は、かつて人事課で給与計算を担当していた職員である。
現在は一億円規模の事業と複数社のプロジェクトマネジメントを一人で担当している。
太田氏が重視するのは、行政職員が当事者意識を持つことだ。
スタートアップ支援を行うなら起業を経験し、空き家解決に取り組むなら実際に空き家を活用してみる——そんな当事者としての体験を重視している。
「塩尻でやってきているのは、自分でまずやってみようということです。私も塩尻市振興公社への出向時代に営業をやってきました。」(太田氏)。
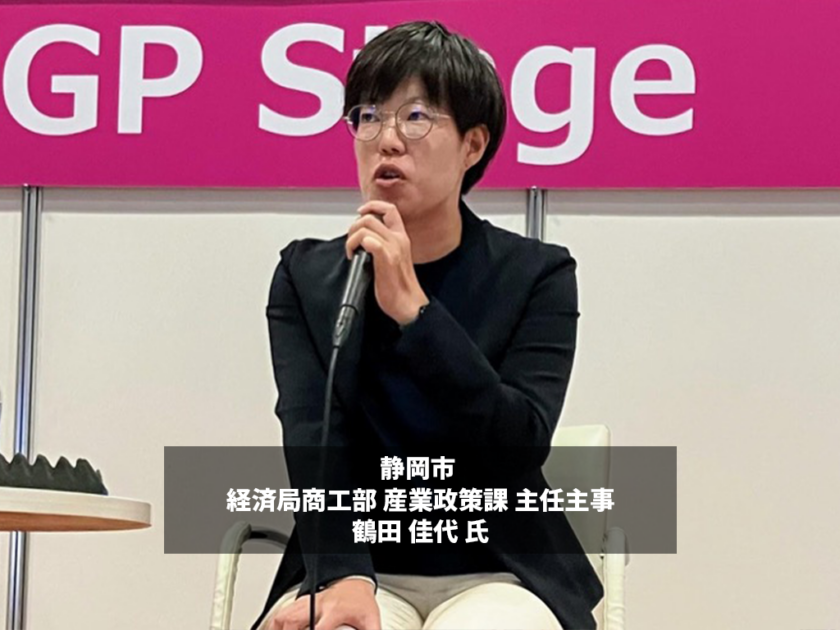
静岡市でも同様のカルチャー変革が起きている。産業政策課では軽装での勤務が定着しつつあるという。
「産業政策課も含む経済局では、昨今スタートアップ企業の方に見られるシャツにジャケットといったスタイルが広がっています。気軽に話しかけていただけることも意識しているようです。」(鶴田氏)。
群馬県の穗坂氏も、スタートアップとの協働から得られる学びの大きさを強調する。
「動けば動くほどレスポンスがある仕事だと改めて思いました。スタートアップの方々のフットワークの良さや成長意欲をすごく感じています」(穗坂氏)。
塩尻市では「リテラシー」「ファイナンス」「当事者意識」の3つの要素を職員が身につけることで、真のイノベーションパートナーを目指している。これらの変化は、全国の自治体職員にとって新たなロールモデルとなりつつある。
企業との協業で見えた課題と可能性

4つの自治体が企業やスタートアップとの協業を深める中で、日本特有の課題と新たな可能性が明らかになってきた。
特に海外スタートアップとの連携を進める群馬県の経験からは、日本企業のマインドセット転換の必要性が浮き彫りになっている。
群馬県が欧州のイノベーション機関 EIT と連携して進めるプログラムでは、日本企業と海外スタートアップの関係性に大きな課題があることが判明した。
穗坂氏は、企業とスタートアップの関係性について課題を指摘した。
日本企業の多くが受け身の姿勢で、海外スタートアップが求める対等なパートナーシップを築けていないという。
「企業の方からすると、スタートアップのリストはないのか、スタートアップからどんな提案をうちはもらえるんだという、結構受け身の姿勢だったり、ちょっと上から目線みたいなところを感じる部分が正直なところあります。日本の企業が何を提供していただけるのかをスタートアップに示していかないと最終的な形の良い協業には結びつかない」(穗坂氏)。
こうした課題に対して自治体は独自の解決策を見出している。
仙台市では、防災という共通課題を軸にした「仙台防災テックイノベーションプラットフォーム」を構築し、自治体・企業・研究機関を含む303の会員が参加する巨大なネットワークを形成している。
塩尻市のアプローチはさらに実践的だ。
太田氏は、予算に制約がある一方で、ユニークなプロジェクトを実証フィールドとして提供できる点を強調する。
「自動運転だったりナノテクだったり、そういったユニークなプロジェクトで試したいテクノロジーがあれば、ぜひうちのフィールドをテストベッドとして使っていただきたい」(太田氏)。
この「テストベッド」としての自治体の役割は、企業とスタートアップの関係を根本的に変える可能性がある。従来の発注者と受注者という上下関係ではなく、共同で実証実験を行うパートナーとしての関係性を構築できるからだ。

これらの取り組みから見えてくるのは、自治体が単なる行政サービス提供者から、イノベーション創出のプラットフォーマーへと役割を転換していることだ。
企業とスタートアップを結ぶハブとしての機能を果たし、それぞれが持つ資源や知見を効率的にマッチングする仕組みを構築している。
4つの自治体の取り組みからは、地域課題解決に向けた新しいアプローチが見えてきた。
従来の「お役所仕事」の枠を超え、民間企業やスタートアップと協働する自治体職員たちの変化は日本のイノベーションエコシステム全体に大きな影響を与える可能性を秘めている。
自治体が持つユニークなアセットの活用方法も明確になってきた。
仙台のナノテラス、群馬の製造業基盤、塩尻の実証フィールド、静岡の積極投資——それぞれが地域の特性を活かした独自の価値提案を行っている。
従来の自治体は規制や許認可の主体として認識されることが多かったが、今や実証実験のパートナー、イノベーション創出の協力者として位置づけられている。
これらは東京一極集中とは異なる、分散型イノベーションモデルを示すことになるのではないだろうか。







