
仙台発グローバル挑戦へ DATERISE!2025ピッチコンテストで東北11社が熱戦

仙台市主催の初の大規模グローバルスタートアップイベント「DATERISE!2025」が8月23日に開催された。「SENDAI to Global!」をテーマに、仙台・東北から世界に羽ばたくスタートアップ、学生起業家、未来の挑戦者たちを応援する多彩なコンテンツが展開された。
コンテンツは11社によるピッチコンテストを軸に、元メジャーリーガー岩隈久志氏による基調講演、フランス・エコールポリテクニークの起業家による実践的セッション、東北発グローバル企業によるパネルディスカッションなど多彩なプログラムを展開。
メイン会場のウェスティンホテル仙台には52団体がブース出展し、隣接するYUINOSでは家族連れも楽しめる体験型の「縁日ENNICHI」や学生向けワークショップも同時開催された。

メインコンテンツとなるピッチコンテストでは、27社の応募から選ばれた東北に拠点を持つ11社が決勝に進出し、6分間のプレゼンテーションで事業の可能性を競った。審査は藤本あゆみ氏(一般社団法人スタートアップエコシステム協会代表理事)、Chris Burry氏(US Market Access Center Co-CEO)、合田ジョージ氏(ゼロワンブースター代表取締役)、John Lim氏(Meet Ventures Partner)、横田有香子氏(One Capital Healthcare Partner)をはじめとする投資家・経営者から選出された5名のグローバル審査員が行った。
優勝(NTT EAST賞):AI で放射線治療を革新するアイラト(AiRato)

NTT EAST賞を受賞したアイラト創業者の角谷倫之氏は、放射線治療分野で世界をリードする研究者だ。東北大学医学部発のスタートアップとして「放射線治療ですべてのがん患者を救う」というミッションを掲げ、AI を活用した革新的な治療計画システムを開発している。
角谷氏は国内最大の放射線治療研究室の責任者として長年この分野の研究を牽引してきた。名古屋大学医学系研究科博士課程修了後、スタンフォード大学やカリフォルニア大学での研究員・客員助教を経て、現在は東北大学病院放射線治療科で病院講師として勤務している。
現在、がん患者の半数が利用する放射線治療において、IMRT(強度変調放射線治療)が主流となっている。この技術は細いビームを100から200ショット様々な角度から照射してピンポイントでがんを治療する画期的な手法で、東北大学の例では従来の7割程度だった制御率が95%まで劇的に改善している。
しかし、IMRT には大きな課題があった。治療計画の作成に6時間もの時間がかかることだ。角谷氏は現状の問題点を詳しく説明する。CT 画像200枚に腫瘍や危険臓器を1枚1枚ミリ単位で描画する作業に2時間、200ショットの照射設計に3時間、安全確認に1時間という膨大な作業が医療スタッフの負担となり、治療件数の増加を阻んでいた。
角谷氏が開発した AI システムは、この課題を根本的に解決する。患者の CT 画像を入力するだけで、従来6時間かかっていた全工程をわずか20分で自動的に完了させる。実際のプロトタイプでは前立腺がんの治療計画を20分で作成し、放射線治療専門医が作成した計画と同等の品質を実現している。

同システムの導入効果は多岐にわたる。同社試算によれば、救える患者数を約5倍に増やし、年間1980時間の業務削減、病院の年間9000万円増収を実現できる計算だ。現在、国内14の基幹病院でテスト評価を実施しており、医療現場からは早期の臨床導入を求める声が多数寄せられているという。
激戦の末、NTT EAST賞として海外展開を本格的に後押しする特典を獲得した角谷氏に、優勝直後にインタビューを行った。
――優勝おめでとうございます。率直な感想をお聞かせください。 **角谷氏:**第一回目の優勝者ということで、とても光栄です。 ――優勝特典としてシンガポール展開の機会を得られましたが、どのように活用される予定ですか? **角谷氏:**シンガポール進出は検討していなかったんですが、シンガポールはアジアのスタートアップのハブでもあります。例えば有名な医療機関に入ることで、アジア各国への波及効果もあるでしょうし、良いきっかけになると思います。実際に行きながら、シンガポール自体を攻めるのか、シンガポールを拠点に近くの国を攻めるのか、解像度を上げてやっていけたらと思います。 ――海外でも同様の課題があるという認識でしょうか? **角谷氏:**すでにマレーシアの大きい民間病院や公的な病院でテストさせていただいているのですが、課題は全く同じになっています。非常に期待されている技術かなと思うので、日本で開発を進めていったら、アジアでも同じように有用だと思います。 ――この事業に取り組むきっかけを教えてください。 **角谷氏:**私は放射線治療科に所属しながら AI 開発も手がけてきました。放射線治療の臨床現場では、誰もが感じる課題だったんです。これを AI 開発というアプローチで解決できるのではないかと思って、10年くらい前から開発を開始して、やっと今形になってきたという状況です。 ――今後の意気込みをお聞かせください。 **角谷氏:**今回は支援いただき、我々としてはもともと創業期から海外展開を前提にすべてを動かしてきました。開発も全部英語で作っています。やっと時期が来たというところなので、仙台市のサポートを受けながら、本当にグローバルで勝ち切りたいと思っています。
空気中の CO2 を低コストで回収する「HumiDAC」

CaptureSmith の松田由樹氏は、東北大学発の膜技術を用いた二酸化炭素回収システム「HumiDAC(ユミダック)」に関して発表した。カーボンニュートラル社会では石油に代わる炭素資源として空気中の CO2 が重要になるが、従来の DAC(Direct Air Capture)技術は空気中の CO2 濃度が0.04%と低く、特に湿潤地域では加熱コストが膨大になる課題があった。
松田氏が提案する解決策は、東北大学福島教授が開発した「ユミフレクト膜」の活用だ。この膜は CO2 は透過させるが水は透過させない特性を持ち、従来の DAC 技術の前処理として適用することで加熱コストを大幅に削減できる。松田氏は湿潤な気候でも低コストで DAC を実現でき、湿潤地域でも250ドル程度で回収できる強みがあると説明した。
同社は1年半後の会社設立を予定しており、まず日本でユミフレクト膜の販売を開始し、その後 HumiDAC 全体の販売、海外展開へと段階的に事業を拡大する計画だ。展開先として想定する東南アジアは湿潤な気候であり、同技術の優位性を最大限に活かせる市場となる。
廃漁具を「未来の資源」に変える循環型素材

amu の加藤広大氏は、海洋プラスチックごみの約60%を占める漁業関連ごみに着目し、廃棄漁具を原料とした循環型素材「amuca®」の事業を展開している。気仙沼に移住して立ち上げた同事業について加藤氏は、気仙沼から世界に通用する事業を行うとの強い意志を語った。
事業のきっかけは気仙沼の居酒屋で出会った遠洋漁業50年のベテラン漁師との会話だった。漁師が語ったマグロ漁のストーリー、世界を1周して南アフリカの美しい光景を見ながら釣り上げたマグロが食卓に届くまでの物語に感動し、このようなストーリーを多くの人に届けられるのではないかと考えたのが最初のきっかけだという。
同社は全国の漁業者から使用済み漁網を古物として買い取り、ケミカルリサイクルによって高純度の糸を生産、布に加工してメーカーやブランドに販売している。漁業者から回収、分別、洗浄、破砕、リサイクル、ブランディングまでを一気通貫で行う点が特徴で、石油由来のバージン材とほぼ同等のコストスペックを実現している。
製品には詳細なトレーサビリティ情報をタグに込めており、いつ、どこの誰から、何をどのようにリサイクルしたかがすべて可視化される。現在はゴールドウィン、仙台うみの杜水族館、大阪万博でのアーバンリサーチとの協業など、着実にトラクションを積み上げている。加藤氏は価値のないものはない、そんな世界をつくることを目指し、まずそれを漁具から体現していきたいと語った。
未利用油から機能性成分を製造する独自技術

ファイトケミカルプロダクツの加藤牧子氏は、植物油製造時に発生する未利用油から機能性成分を抽出し、バイオ燃料を製造する技術について発表した。東北大学で20年間培った研究成果をもとに、2人の女性リーダーを中心とした15名のチームで資源循環型社会の実現に挑戦している。
同社の強みは「イオン交換樹脂法」という独自技術にある。従来は水処理などで使われてきたイオン交換樹脂を油の中で使えるようにした技術で、未利用油とアルコールを反応させることで、油の成分をバイオ燃料に変換し、同時に機能性成分を高純度で回収できる。加藤氏は従来の熱をかける作り方に対し、熱をかけない製法により省エネルギーで成分の回収率も高くなると説明した。
ビジネスモデルは2軸で展開している。1つ目は米ぬか由来の機能性成分(スーパービタミン E、バイオパラフィン、フィトステロール)を食品、化粧品、サプリメントメーカーに販売すること。2つ目は技術ライセンスやプラント導入支援による設備展開だ。
昨年度の大型資金調達により自社設計・建設のパイロット設備を完成させ、実証稼働に向けて準備を進めている。加藤氏はこの技術を日本から世界へ進める取り組みを今後も続けていくと語った。世界市場規模は約8兆円規模とされ、技術普及により年間5,000万トンのCO₂削減が期待されるという。
10ミクロン精度の金属3Dプリンティング技術

3D Architech の工藤朗氏は、10ミクロンスケールでの金属構造製造を可能にする革新的な3D プリンティング技術について発表した。同社はデータセンターの冷却効率向上と水素生成効率の改善という2つの領域に注力している。
従来の金属3D プリンターは1台1億円程度の大型装置のため解像度に限界があったが、工藤氏の技術は本来プラスチック用の3D プリンターを使用し、有機材料と独自の化学プロセスをコア技術とする。まずゲル状の構造物をプリントし、その後の処理で金属構造に変換する仕組みだ。
この技術によりデータセンターでは冷却コストを約50%削減、水素生成効率を約30%向上できると工藤氏は説明している。現在は企業からの共同開発で収益を上げており、来年末までに生産ラインを構築し、その後ライセンス事業も展開する計画である。
5つの分野に展開するナノ粒子生成技術

ナノフロンティアの井上誠也氏は、東北大学で30年以上研究された「再沈殿法」によるナノ粒子生成技術を活用し、4月創業ながら5つの事業領域で展開している。
メインターゲットは PFAS 検出試薬だ。2026年4月に日本の水質基準(PFOS/PFOA合算50ng/L)が厳格化されることを受け、同社の有機ナノ色素によりリアルタイムかつ低コストで PFAS を検出できるシステムを開発している。
その他の領域では、蓄電池用有機ナノ電解液でコスト半減、冷却液へのナノ粒子添加でデータセンター冷却電力最大約90%削減、水素輸送でのエネルギーロス半減、キャリアフリー抗がん剤開発など幅広く展開する。創業1年目からドイツ、アメリカ、台湾などでの海外展開を計画している。
水を使わない革新的デンプン加工技術
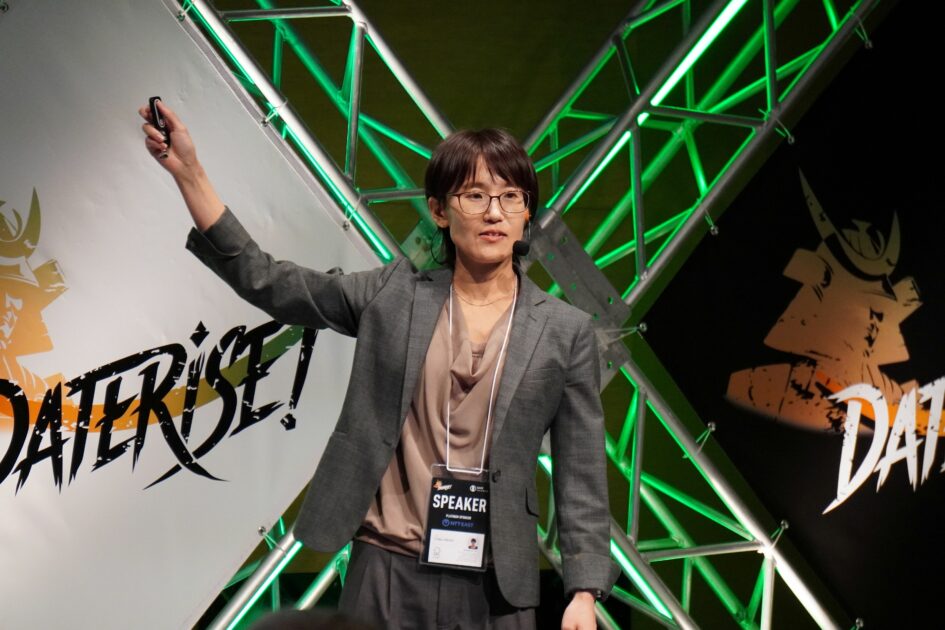
アルファテックの曵地知夏氏は、水を使わず粉砕だけでデンプンをアルファ化できる独自技術「Amorfast」について発表した。従来は水を加えて加熱する必要があったが、同技術により処理コストを最大約10分の1に削減できると説明した。
生の米を装置に投入し、粉砕処理だけで炊飯状態の米粉が生成される。このアルファ化米粉はそのまま食用可能で、グルテンフリー食品での小麦粉代替やケアフード活用など幅広い用途が期待される。
世界市場は約2000億円規模だが、低コスト性により従来参入できなかった領域も含めて大幅な市場拡大が見込める。ビジネスモデルは自社製造販売と粉砕機のライセンス事業の2軸で展開する。
皮膚からの無痛投薬システム

bionto 代表取締役の妹尾浩充氏は、生体イオントロニクス技術を活用した革新的な投薬システムについて発表した。人体の60%を占める水分中のイオンの動きを制御することで、皮膚から痛みなく薬物を投与する技術を開発している。
従来の注射による投薬は特定の場所で医師しか実施できず、飲み薬には嚥下の問題や副作用、そもそも経口投与できない成分があるという課題があった。biontoの技術では金属を使わない安全な材料で作られたバイオ発電スキンパッチと高速振動デバイスの2つのコンセプトプロダクトにより、自宅で誰でも確実に皮膚から投薬できるシステムを目指している。
応用範囲は医薬品投与にとどまらず、スキンケア、頭皮ケア、皮膚からのサプリメント成分導入など一般商品への展開も計画している。妹尾氏は誰もが自分らしく生きることに寄り添い、すべての人がより長く健康に生きられる社会の実現に貢献したいと語った。
水を使わないデカフェ技術で市場開拓

ストーリーライン代表取締役の岩井順子氏は、超臨界二酸化炭素を用いた革新的なデカフェコーヒー製造技術について発表した。東北大学との共同研究により開発した技術で、従来の水を使った抽出法と異なり、カフェインのみを除去して有効成分を保持できる。
従来のデカフェ製造では豆を水につけてカフェインを抜く際に、糖や脂質といった美味しさの成分も流出してしまう問題があった。岩井氏の技術は水を使わない画期的な手法により、ほとんど通常のコーヒーと区別がつかない高品質デカフェの製造を可能にした。
さらに「カフェインコントロール」という新しいコンセプトを提案し、時間帯や体調に合わせてカフェインを選ぶ価値を訴求している。東京日本橋で展開するブランド「チューズコーヒー」では約半数の客がカフェイン量を調整する行動を取っており、デカフェ市場拡大の可能性を実証している。将来的にはコーヒー生産地での現地生産を計画し、2029年に50億円の売上を目指している。
防衛・災害・物流に対応するドローンシステム

イームズロボティクス代表取締役社長の曽谷英司氏は、福島県南相馬市を拠点に「東北から福島から日本を守る」をコンセプトとしたドローン事業を展開している。物流、点検、警備、災害対応に加え、防衛分野での市場拡大を見据えている。
福島県はドローン物流特区に選定され、優先的な規制改革が進んでいる。災害対応では昨年の能登半島地震で観光庁と連携し、ドローン撮影データの共有システムを初導入した。可視光カメラ、赤外線カメラ、スピーカー、物件投下機能を備えた災害専用ドローンを開発している。
防衛分野では経済産業省から総額26.5億円の補助金を受け、マルチコプター、長距離 VTOL 機、1人で10台から20台を操縦できるシステム、AI 搭載自律飛行システムを開発中だ。曽谷氏は日本の自国部品によるドローン製造体制の重要性を強調し、システムと AI の総合的アプローチで世界展開を目指している。
A4 サイズのポータブル DJ 機で世界進出

ミューシグナル代表取締役の宮崎晃一郎氏は、A4 サイズのポータブル DJ 機「FJ1」の世界展開を発表した。従来の DJ 機材は大きく重たく設置が困難で DJ 普及の壁となっていたが、モバイルバッテリー駆動で大音量スピーカー内蔵の画期的なデバイスを開発した。
2024年のクラウドファンディングでは1758名から1億円超を調達し、日本語サイトのみにも関わらず、アメリカ、ドイツ、イギリス、アルゼンチン、シンガポール、タイ、マレーシアなど世界各国から購入問い合わせが殺到している。
8月27日の出荷開始を控え、海外ディストリビューターや販売パートナー、インフルエンサーとの連携を求めている。海外ではモバイル DJ として出張で稼ぐ文化があり、大型機材の半分から3分の1の価格となる10万円前後での展開により、仙台発ハードウェアで世界市場開拓を狙っている。
仙台発エコシステムの新たな一歩
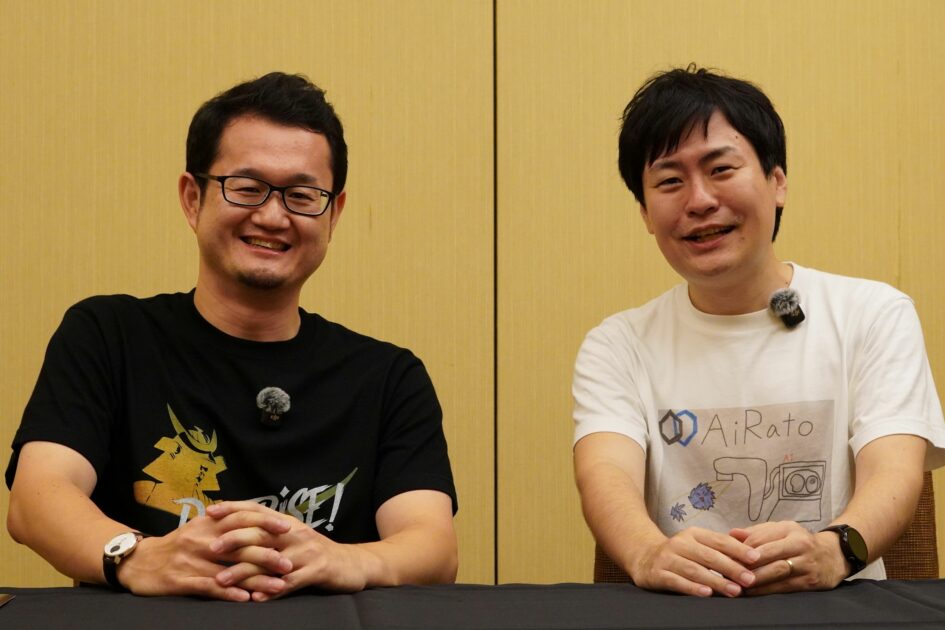
最後に、イベント運営を担当した仙台市の白川裕也氏は、今回のイベントについて、想定を上回る参加者が集まったことで、地域としても起業やグローバル挑戦への期待感やワクワク感が醸成されてきたと評価している。
「震災の後は、小さくてもいいので起業する人を増やそう、一歩を踏み出す人を応援しようということで、技術面はそれほど強くありませんでした。起業する人が増えてきて、社会起業家の人たちを応援し、大学発スタートアップも増えてきて、厚みが出てきました。少し前もグローバルを狙いたかったのですが、まだそういうステージではなかった。ようやくグローバルにも行けそうだ、グローバルに行かないといけないという空気感も出てきたので、今年DATERISE!2025を始めて、仙台から世界への挑戦を後押しする機運を作れるようになったと思います」(白川氏)
DATERISE!2025は仙台・東北のスタートアップエコシステムの新たな一歩を刻むイベントとなった。優勝したアイラトをはじめ、各社の今後のグローバル展開に注目だ。







