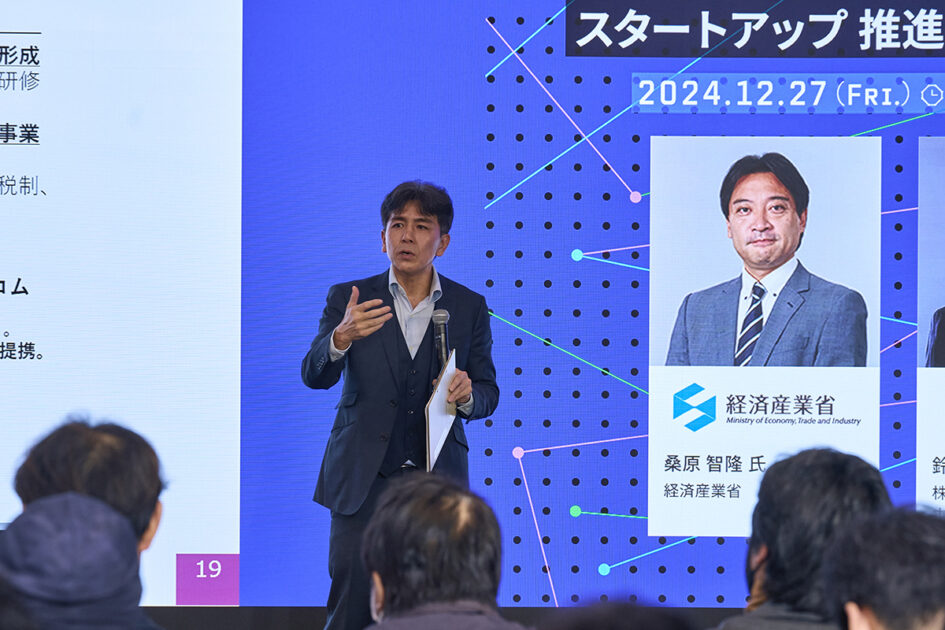経産省が描く「日本のスタートアップエコシステム」の現在地と未来【01Booster Conferenceレポート】

昨年末に開催された「01Booster Conference」最後のセッションは、経済産業省 イノベーション創出新事業推進課の桑原課長を特別ゲストに迎え、スタートアップと大企業の共創による日本のポテンシャルを活かしたイノベーション創出の可能性を官民の知見を融合させた視点で探るものとなりました。
スタートアップ育成5か年計画から2年を経過した現時点における日本のスタートアップエコシステムの現状は?更なるイノベーション創出と経済構造改革推進に向けた今後のスタートアップ政策についても触れ、参加者に向けて現状と未来のビジョンを共有するものとなりました。
スタートアップ政策の現在地
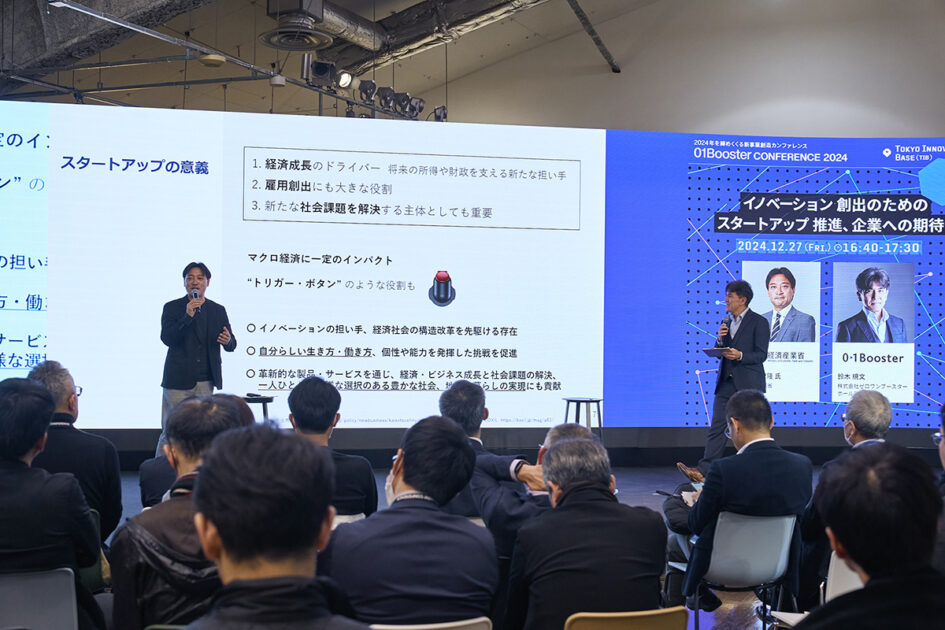
2022年に始まったスタートアップ育成5か年計画は、「裾野の拡大」という点で、日本のスタートアップエコシステムに大きな影響を与えました。
人材、資金、オープンイノベーションの三本柱で進められている政策は、予算面でも2022年度補正予算の約1兆円、2023年度補正予算の約2,300億円、そして今年度の経済対策での約2,000億円と、大規模な投資が継続されています。スタートアップ政策推進の流れは、岸田政権から石破政権に移行した現在も、揺るぎない方針として維持され、成果も現れ始めています。資金調達額を見ると、米国や中国、英国など海外市場が低迷する中、日本市場は踏みとどまっている状況です。
また、スタートアップの数という点でも3年前の約1万6,000社から約2万2,000社(累積、2023年)へと大幅に増加。その中でも大学発スタートアップは、同時期に約3,300社から約4,200社へと大幅に増加しており、各大学がそれぞれの強みを活かした展開を見せています。バイオ、ライフサイエンス、素材、量子技術、ゲノムなど、専門性の高い分野での起業が活発化しているのです。
大型IPO(株式公開)の発生、ユニコーン企業(時価総額で10億ドル相当の評価を持つ企業)の増加など、スタートアップの「芽」は着実に成長しています。日本はユニコーン企業が少ないと言われがちですが、グロース市場上場後の企業も含めると70社強に達しています。ディープテック分野では、上場よりもシリーズ後期の資金調達を選択する企業も多く、実質的な成長企業数はさらに多いと考えられます。
こうした傾向もあり、最近では日本のスタートアップエコシステムの発展に、海外からの注目も集まりつつあります。AI関連企業への投資や、海外ベンチャーキャピタルやアクセラレーターの日本進出が増加傾向にあります。また、相次ぐ現在、ユニコーン企業の予備軍的な存在として、企業価値500~1,000億円の企業が30社程度、企業価値100~500億円の企業が270社程度存在する状況です。
こうしたスタートアップエコシステムの「裾野」の拡大から、今後は「高さ」の創出と「継続」へと政策を推進していこうと取り組んでいるのが、経済産業省のイノベーション創出新事業推進課です。
民間経験が変える行政アプローチ

今回壇上に上がった桑原氏は、異色の経歴の持ち主です。20年にわたる経産省でのキャリアを経て、スタートアップのOrigamiに転職。その後、ベンチャーキャピタルのScrum Ventures Groupでの活動を経て、2024年夏に経産省に戻るという、前例のない経歴を持っています。桑原氏は当時の決断を、以下のように振り返ります。
「(官の)政策側に素晴らしい仲間がいる中で自分のバリューを出す方法を考えた時、戦略を描くだけでなく、未来投資の主役である民間側の『うねり』を作る方に自分はチャレンジしてみたいと思いました」
現在、経産省イノベーション創出新事業推進課では約25名の人員の内、半数以上が民間からの人材になっているそうです。大手自動車メーカーやインパクト投資を行うVCからの出向者など、多様な背景を持つメンバーが政策立案に関わっています。「スタートアップ政策こそ、オープンイノベーションが必要」と桑原氏は強調します。
次なるステージへ:高さの創出と継続
スタートアップエコシステムの裾野が広がりを見せる中、経済産業省は次のステージとして「高さ」の創出と「継続」を掲げています。これは、企業価値が1桁大きな企業を創出し、ユニコーン企業が持続的に生まれる環境を整えることを意味します。特に注目されているのが、ディープテック分野です。現在、アメリカではユニコーン企業900社以上のうち55%がディープテック関連企業である一方、日本のユニコーン企業8社のうちディープテック企業はわずか2社に留まっています。
日本の科学技術力の高さに鑑みると、この分野には大きな成長余地があると見られています。桑原氏は「2025年は民間調達や公共調達のギアを上げる変化の年にしたい」と位置付けています。スタートアップの製品・サービスを、民間企業に加えて政府や自治体が積極的に調達することで、需要の創出、民間企業の新規事業創出や地域の社会課題の解決にもつなげていくことが重要との認識です。先進自治体では、東京都のキングサーモンプロジェクトや福岡市の先端技術公共調達サポートなど、実証の場を提供する取り組みが始まっています。
エンジェル税制も大きく拡充されます。これまでは当年中の再投資が求められていた譲渡益の税制優遇について、再投資期間を複数年に延長。より柔軟な投資活動を可能にすることで、個人投資家からスタートアップへの資金流入を促進します。
さらに、産業革新投資機構や中小機構といった官民ファンドを活用し、ベンチャーキャピタルのファンド・オブ・ファンズや一部直接投資も実施。エコシステムの本格的な形成に向けて、資金調達額とユニコーン数が相乗的に持続的に伸びていくことが必要と考えています。
スタートアップと大企業の新しい関係性

スタートアップと大企業の関係性は、この10年で大きく変化しました。かつては「取引実績」を過度に重視する傾向があった大企業も、今では「Power to Scale(スケールする力)」とスタートアップの革新性を組み合わせることで、新たな価値創造を目指すようになっています。
Power to Scaleとは、大企業が持つ社会的信用、確立されたオペレーション能力、豊富な人材や資金といった経営資源を指します。一方、スタートアップは未来志向の革新的なテクノロジーやビジネスモデル、そして圧倒的なスピード感を持っています。この両者の強みを組み合わせることで、より大きなイノベーションの社会実装が可能になる、という考え方です。
「大企業とスタートアップは、どちらが良いか悪いかではなく、合理的な行動原理が異なるため、強みを組み合わせることが重要」と桑原氏は指摘します。異なるカルチャーや行動原理を持つ両者が、お互いの長所を活かしながら、不足する部分を補い合う関係性を構築することが重要だと説明します。
この認識のもと、経済産業省は2025年に向けて、大企業によるスタートアップの製品・サービスの調達・購買を通したオープンイノベーション手法に関する新しいガイドラインの策定を進めています。知的財産権の取り扱いや検収要件など、両者にとってフェアな契約の在り方を示すことで、協業を促進する狙いです。
スタートアップ側からすれば、大企業との取引は売上計上が可能で、補助金と比べてより事業としての継続性が期待できます。一方、大企業にとっては、スタートアップの製品・サービスの調達・購買を活用し効果検証の機会を増やすことで、自社の経営課題の解決に資するスタートアップを効率的に選定し、イノベーション創出に繋がるというメリットがあります。
2025年に向けた展望

2025年は日本のスタートアップエコシステムにとって重要な転換点となりそうです。春から開催される大阪・関西万博の期間中、9月17~18日は、約4000平米の「WASSE」スペースを活用したGlobal Statrtup EXPO 2025の開催が予定されています。このイベントは、日本のスタートアップの魅力を世界に向けてショーケースする重要な機会となります。
経済産業省が描く将来像は、単なるスタートアップの育成にとどまりません。スタートアップエコシステムの発展は、働き方改革や生き方の多様化といった社会変革のトリガーとしても期待されています。実際、人材面では、転職者のうち大企業からスタートアップへの割合が約25%に増加したり、40歳以上の方のスタートアップへの転職者数が10年前の7倍に増加したりしているとの調査もあります。
桑原氏の語る「未来と自分は変えられる」という信念のもと、大企業とスタートアップ、行政と民間、それぞれの強みを活かした垣根を超えた協力関係の構築により、日本のポテンシャルと活かしたイノベーション創出に向けた新たな章が始まろうとしています。