
スタートアップでのキャリアを考える——現役プレイヤーが語る、人材獲得と育成の最前線
スタートアップ育成5か年計画の策定や、東京都によるグローバルイノベーション創造拠点の整備など、スタートアップ支援の機運が高まっています。一方で、スタートアップエコシステム協会が2024年5月に実施した調査によると、資金調達に加えて、採用や組織構築といった面でも多くのスタートアップが課題を抱えていることが明らかになりました。約400人から寄せられた回答からは、ステージごとに異なる課題が浮かび上がり、特に成長期において人材に関する課題が顕在化する傾向が見られます。
スタートアップで働くということは、具体的にどのような選択なのでしょうか。MUFG STARTUP SUMMITで開催されたセッション「スタートアップ領域での人材獲得・育成に求められるもの」では、スタートアップエコシステム協会代表理事の藤本あゆみ氏、Beyond Next Ventures株式会社 代表取締役社長の伊藤毅氏、Almoha COO / Startup Culture Lab. 所長の唐澤俊輔氏が登壇。スタートアップの人材戦略について議論を展開しました。
(聞き手:株式会社ゼロワンブースター ゼネラルマネージャー 石田雄彦)
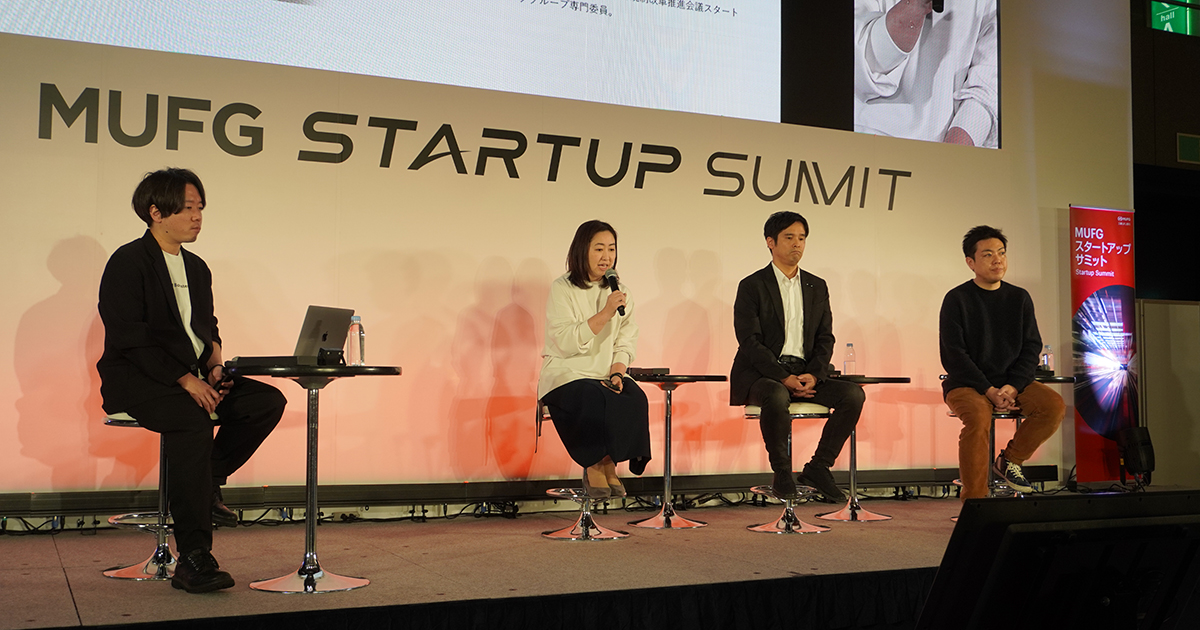
なぜ今、スタートアップという選択肢が注目されているのか?
「ここ2、3年で、スタートアップで働くということが一般的な選択肢として認識されてきています」と語るのは、スタートアップカルチャーラボを主宰する唐澤氏です。
「2017年に私自身がスタートアップに移った時は、大企業から非常に勇気を持って飛び込んだという感覚でした。当時はまだ『ベンチャー』という言葉を使っていたような時代でしたが、だいぶ経ってきていろんな形でスタートアップという言葉が使われるようになっています」(唐澤氏)
この認識の変化の背景には、給与水準の向上があります。「最近は日経新聞の記事でも、給与において一般企業とスタートアップを比べたらほぼ同じか、スタートアップの方が上回ってきたという報道も出ています。転職先のランキングでもスタートアップという選択肢が上がってきています」と唐澤氏は説明します。

Beyond Next Venturesの伊藤氏も、特にディープテック領域での変化を指摘します。
「かつては前職の給与を下げる代わりにストックオプションを付与して採用するケースが多かったのですが、今はそういう状況ではありません。特に幹部など重要なポジションの場合、前職の給料以上を出して採用することも、ディープテックでは珍しくなくなってきています」(伊藤氏)
その背景には、ファンドの大規模化があります。「これは日本全体に言えることですが、ファンドの規模が大きくなっており、私たちの3号ファンドも比較的、大きな規模となりました。スタートアップがかなり大きな調達をここ数年できるようになってきた結果、会社の財務的な余裕が出てきているというのも背景」と伊藤氏は説明します。

大学発スタートアップの増加も特徴的です。「大学が、研究成果の事業化へのエコシステムの重要性を理解して、各大学で大学発スタートアップを何社作るかという目標を掲げるようになってきています」と伊藤氏は指摘します。
「若い研究者の方が自分の研究成果をちゃんと実用化するために起業されるケースや、研究者とコンサルティング業界などのビジネス経験者が共同で創業するといったケースが増えています」(伊藤氏)
2003年からベンチャー投資を始め、2008年からディープテック投資を手がける伊藤氏は、この変化を実感しています。
「2008年当時は、シニアな研究者の方が余生の研究費のために会社を作るというケースが本当に多かったのと、競争的資金をもらうために会社を作る、研究開発のために会社を立ち上げるというケースが多かったのですが、最近はそういう目的ではなく、若い研究者の方が自分の研究成果をちゃんと実用化し世の中に貢献したい考え起業されるケースが増えています」(伊藤氏)
さらに、政策面での支援について、「スタートアップ育成5カ年計画が出てから全然ギアが上がりました」とスタートアップエコシステム協会の藤本氏は語りました。
「国の中での議論も変わり、それが外に出ることで、政府もスタートアップを応援しているということが伝わり、よく分からないという怪しさのようなものが軽減されてきました」(藤本氏)
藤本氏によれば、特に注目すべきは大学生の意識の変化。「大学生でインターンしたいという人がすごく増えてきました」と指摘しました。一方、「大手志向というのはまだ一部残っています。最近またコンサルファーストという選択が復活してきている印象があります。広く経験を積んでおきたいという、リスクヘッジを意識した選択が増えてきているように感じます」と課題を挙げました。
スタートアップではどのような人材が求められているのか?
「崖から飛び降りながら飛行機を組み立てて生き残る」という表現が示すように、スタートアップでは高い自走力が求められます。唐澤氏は「本当に、何でも自分でやっていく、自走していけるような人が求められます」と説明します。
その背景には、スタートアップ特有の組織構造があります。「日本の大きな組織は前例踏襲型で作られてきており、基本的にはメンバーシップ型で雇用して、新卒が入ってきてジョブローテーションしながら進めていく形です。これは破壊的なイノベーションを起こすというよりも、安定的にしっかりとみんなでオペレーションをしていくという、日本の強みです」と唐澤氏は従来の組織との違いを指摘します。
一方で、スタートアップは常に変化に直面します。「競争環境が変わる、資金調達が予定通りに進まない、といったことは常に起こり得ます。その変化の中で一つ一つルールを作って、その通り働いていても、明日には変わってしまうので、ルールを作ること自体に構造的に意味がない場合があります」と唐澤氏は説明します。
「だからこそ、多様な人が入って、ジョブ型でいろんな専門家が参画し、違う人たちがバラバラな方向を向かないようにミッションとビジョンを作り、イノベーションを起こしていく。それがスタートアップの思想であり、構造的にそうならざるを得ないのです」(唐澤氏)
面接だけではわからないことが多いと感じているが故に、採用の現場ではさまざまな工夫がなされています。例えば、インターンシップを実施し、色々な業務を経験してもらう中で、適正を見極めているといいます。実際のアサインメントや、特定のシチュエーションでどういうアクションをとるかということを見るようにしていると唐澤氏は説明しました。

さらに、Beyond Next Venturesの伊藤氏は、実践的なアプローチについて紹介しました。
「私たちの場合は、ディープテック領域で経営幹部の採用は、失敗したときのリスクが高いです。そのため、採用中にNDAを結んだ上で経営戦略などについて、経営陣と一緒に議論するミーティングを何回か実施して、その方がどう立ち振る舞うか、どういう意見を出せるかを見ています」(伊藤氏)
また、面接時の態度からも多くを読み取ることができます。「何かを会社に要求したり、『どうしてくれるのですか』という質問が多いスタンスの方は、スタートアップ向きでは無く、基本的にその後うまくいかないケースが多いです」と伊藤氏は指摘します。
スタートアップのフェーズによっても、求められる人材像は大きく異なります。「スタートアップの初期を伸ばすのに特化していて、組織が大きくなってくると急にパフォーマンスが発揮できなくなる方もいらっしゃいますし、逆もしかりです」と藤本氏は説明します。
「初期ではタイプが合わないけれど、数十人規模のところで組織を整えるのが得意な方もいらっしゃいます」(藤本氏)
唐澤氏は組織の成長期にも注意が必要と加えました。成長期は、現場が忙しい中で人を採用し、人が増えるとまた忙しくなるので、さらに採用するという循環が起きます。唐澤氏は、「組織に合わない人材が増え、組織全体が下に引っ張られていくという危険な傾向が見えてくる」といいます。
「そういう傾向が見えてきた時に、一旦採用を止めて直すということが必要です。私たちは「スタートアップはカオスである」ということを外に向けて発信し、それを受け入れられる人に来ていただくことが重要だと考えています」(唐澤氏)
スタートアップを選ぶ際は、どのような点に注目すべき?
一方、求職者側がスタートアップを選ぶ際、どのような点に注目すると良いのでしょうか。伊藤氏は、まず財務面の確認を重視します。「最近SNSで過去大きく調達して、結局なくなってしまった会社のリストのようなものがシェアされていましたが、資金調達の履歴や、どれくらい調達したという点は、見た方が良いと思います。」と指摘しました。
伊藤氏曰く、市場環境の変化も大きな影響を与えています。「100億円ぐらいの時価総額で上場するスタートアップに投資していたVCが、ユニコーン企業を目指す会社じゃないと投資しないようになり、最近はIPOが近くレイトステージにも関わらず、IPO時の時価総額が小さいために資金調達ができず、チーム縮小をせざるを得ないような局面も増えてきています」といいます。

また、伊藤氏は、創業者との関係性の理解も重要と語りました。「創業者は当然強い存在で、通常は大株主でもありますから社内の影響力も強く、その方が作ってきた会社なので、それは前提として受け入れる必要があります」と伊藤氏は説明します。
「小規模な組織は大企業に比べて柔軟な面もありますが、規模が小さいからといって、自分の思い通りに何でもできるわけではありません。組織には規模の大小にかかわらず、トップがいて、方針やルールがあります。」(伊藤氏)
特に注意が必要なのは、「入社後に『組織を変えたいが、社長が理解してくれない』という悩みが意外に多い」という点です。伊藤氏は、「そうした状況を踏まえた上で、いかに自分が組織を変えるための力をつけるか、そしてトップと対話しながらトップ自身の考えも変えていくかという視点が重要です。この覚悟がないと、『入社すれば何でも自由にできる』という理想とのギャップに苦しむことになります」と指摘しました。
スタートアップの実態について、唐澤氏は「本当にいろいろと自由なことができるのですが、蓋を開けると不自由な中の自由です。やらなければいけないことも非常に限定されていますし、明確です。その中でいかに自分の持ち味を見せて成果を出していくかというところが重要になります」と説明します。
その上で、唐澤氏は面接時にいかに企業文化を見極めるかについてアドバイスしました。
「課題を話してくれる会社は良い会社だと思います。面接の中でいいところをすごくたくさんアピールすることは、本当にそうなのかと少し怪しく感じます。課題をちゃんと伝えて、その課題を一緒に解決する人を募集するというスタンスの会社だと、入社後にそれほど違和感なく働けると思います」(唐澤氏)
スタートアップへの転職は、どのように準備を進めればよいのか?
実際のスタートアップへの転職準備について、段階的なアプローチを藤本氏は勧めました。
「メディアに載っているところが良いと決め打ちせずに、まずは自分の目でいろんなところの話を聞いていただきたい。そして副業からステップを小さく進めていくのがおすすめです。いろんな形で関わり方を持っていただけますから」(藤本氏)
特に大手企業からの転職を考える場合、この段階的なアプローチは有効です。「今はもちろん副業ができない会社もありますが、できる方は、それで自分がどこで一番力を発揮できるのか、もしくはしたいのかを見極められるチャンスです。スタートアップのリスクも軽減できます。いきなり転職すると非常にハードルが高くなってしまいますが、その手前のステップを作ることができます」と藤本氏は指摘します。
また、藤本氏は、自身の経験をもとに変化への対応も重要なポイントであると語りました。
「これが一番大事なプロダクトだと言われて全力で取り組んでいたのに、1ヶ月後にデータが良くないからという理由で方針が変わることがあります。私は『そういうものだな』と思って受け止められましたが、それがつらいと感じる人もいます。これだけ積み上げてきたのに、そのサンクコストをどうやって回収するのだろうという思いになると、つらい状況になると思います」(藤本氏)

では、スタートアップでの経験は、キャリアの中でどのように活かせるのでしょうか。唐澤氏は「失敗を恐れない姿勢」を重要なものとして挙げました。
「私は、挑戦することは非常に正しいことだと思っています。確かに失敗することもありますが、積極的に取り組むことが一番学びも多いですし、学んでいく中で成長があります。失敗は誰でもしますが、失敗した先に成功するまでやり続ければ、全ての失敗は成功のためのストーリーになります」(唐澤氏)
伊藤氏もまた、「大手企業も新しいものを生み出さなければいけない、アントレプレナーシップを持っている人が、もっと社内に必要な状況になっています。そういった意味で、スタートアップの経験者が実は大企業でも重宝される」と指摘しました。
これから、日本社会は人口のピークを過ぎていきます。その中で同じことをしていてはどんどん衰退してしまうと唐澤氏は危惧します。また、「何か変化を起こしていかなければならず、その変化の大きい方を選ぶことが成長につながる」と強調しました。
「イノベーションを起こすとか新しいことを作るということは必須になっています。スタートアップ的な働き方が恐らくどんどん主流にシフトしていくので、そちらを全く見ないという選択肢はなくなっていくのではないでしょうか」(唐澤氏)







