
1700人のイノベーションコミュニティはいかにして作られたか——リコーTRIBUSの社内巻き込み戦略

リコーによる「TRIBUS(トライバス)」は、社内外からイノベーターを募り、リコーのリソースを活用しイノベーションにつなげるプロジェクト。ワークプレイスやイメージング領域にとどまらず、社会の広い分野での課題解決を目指します。資金や先進技術にとどまらず、リコーグループ社員が社内外で得てきた知見を活かしてサポートすることで新しい価値をつくります。
「常に当時の一番関心が低かった自分だったら入るコミュニティかという気持ちで運営しています」。リコーの社内新規事業プログラム「TRIBUS」を運営するリコー TRIBUS推進室 TRIBUSプログラム運営事務局 森久 泰二郎氏は、自身の経験をそう振り返ります。今回は、ゼロワンブースター合田をトークパートナー、川岸を聞き手に、TRIBUSの社内巻き込み戦略についてお話を伺います。
「熱くない」視点からの出発——共感的な運営の原点

「社内の売店に告知ポスターが貼ってあって、アイスクリームを買うために売店に立ち寄ってポスターの前を通りかかったら、誰かに『森久さん、こういうの応募しそうだけどね』という感じで言われたことがありました」と、2019年に開催された初回のプログラム(当時のプログラム名称はRFG CHALLENGE)のことを振り返りました。その時は応募する気もなく、プログラムに関わろうとも思っていなかったのだそうです。
森久氏は当時、初回のプログラム募集イベントの中で過去に森久氏が行った新規事業の取り組みについての社内向けの講演依頼を受ける講演資料を準備するも話は途中でフェードアウトしていったといいます。そのもやもやした気持ちが、その時にたまたま出会った社員たちと共に二つのテーマでプログラムに応募するきっかけとなり、そのどちらのテーマも選考を進んでいくことになったのだそうです。そして翌年、思いがけず事務局のリーダーとしての役割を任されることになったのです。この経験は、プログラム運営の重要な視点となっています。
「RFG CHALLENGEからTRIBUSにリブランディングされる2020年から私が事務局になって、ある意味その熱がない側の社員の気持ちを知っているので、熱がない側の人たちにも『参加してみたら意外と楽しいよ』というのを伝えようと気にしながらやっていました」(森久氏)
では、多様な人材が集まる大手企業において、熱はどのようにしたら生み出せるのでしょうか。
多層的なコミュニティ設計
TRIBUSの特徴的な仕組みの一つが、「サポーター制度」です。現在約400人が登録するこの制度は、新規事業への直接参加以外の関わり方を提供しています。さらにその外側には、約1,700人が参加する「TRIBUSコミュニティ」が存在します。これについて、森久氏は以下のように説明しました。
「最初は何もないところからは集まらないので、当初はイベントなどの中でイベント参加者をコミュニティの方にどんどん入れていって、出て行く人は追わず、来るものはもう何でもウェルカムという感じでやりました」(森久氏)
数百人人程度が集まった頃から自然な広がりを見せ始め、1200人を超えた頃には既存事業部からも「自分たちが何かヒアリングやトライアルをする際に、コミュニティの人たちにお願いすることもできますか」という声が上がるようになりました。
「プログラムのためだけではなく、既存の事業部にとってもコミュニティが価値をもたらせる状態になってきて、人数もどんどん増えていきました」と森久氏は振り返ります。できるだけ一部の熱のある人だけのコミュニティにならないようにしながら、かつ活性化するというバランスをとりながら、TRIBUSのためだけではなく、社内のイノベーション活動に寄与するコミュニティとして機能するよう心がけているのだそうです。
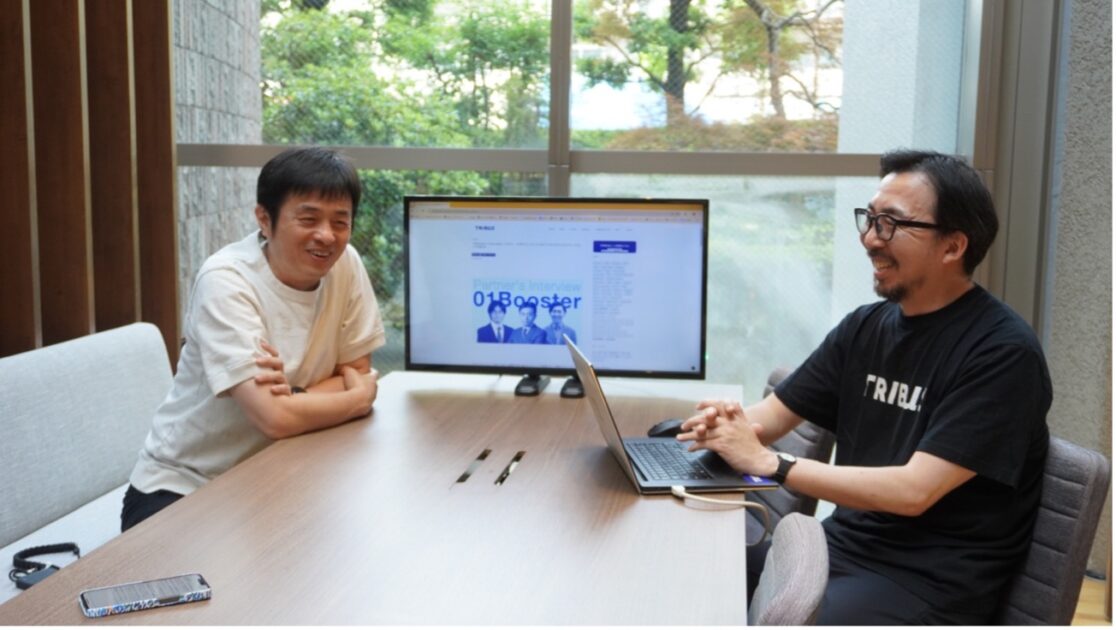
カタリストが担う架け橋の役割
スタートアップ支援人材「カタリスト」の存在も、TRIBUSの重要な特徴です。
「TRIBUSではそういった方たちの存在もとても重要だと思っています。その方々は自分でアイデアを持っていくというわけではなくても、挑戦するところをサポートしていきたいという思いがあります」(森久氏)
カタリストはスタートアップの伴走支援を通じて、ベンチャー的な考え方や価値観を吸収していきます。「スタートアップさんと接すると、カルチャーショックを受けることが多いです。『決定スピードがこんなにも違うのか』と本当にびっくりすることがあります。だからどちらも経験する人は多分すごく強くなると思います」
そうした経験を積んだカタリストが社内に増えていくことで、新規事業やオープンイノベーションを推進しやすい土壌が形成されていくことが期待されています。
参加のグラデーション—多様な関わり方の提供
「他の会社さんを見ても、イノベーション人材というか、自分で企画してゴリゴリやっているという人たちは、普通に人口比率的には多くないと思います」と01Booster合田は指摘します。TRIBUSの特徴は、そうした現実を踏まえた上で、多様な参加形態を用意していることです。
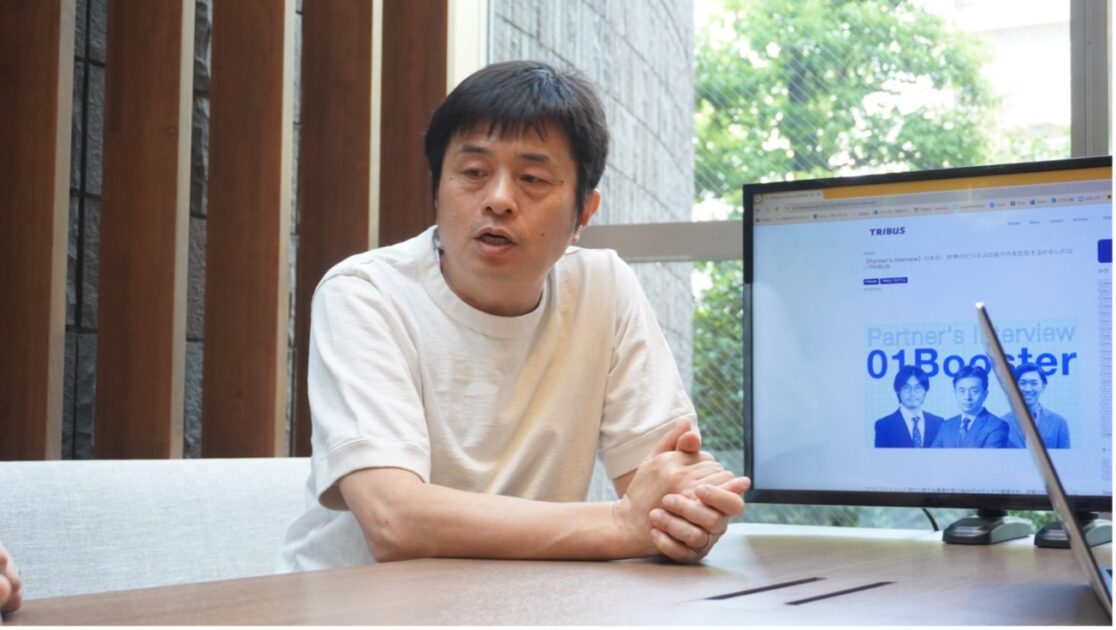
「ちょっと興味があるから少し関わってみたいという人たちが参加できる」というのがサポーター制度の本質です。実際の参加者の中には、サポーター経験を経て翌年には事業提案者として参加する者もいれば、「私はサポーター側の方が向いているな」と気づく者もいます。
2019年から導入された社内副業制度も、こうした多様な参加を可能にする重要な基盤となっています。「必ずしもビジネスアイデアで応募するだけではなく参加できる」形を作ることで、より多くの社員が新規事業創出に関われるようになりました。
デジタルを活用したコミュニケーション戦略
コミュニティの活性化に向けて、TRIBUSは新しい取り組みも積極的に導入しています。2023年12月からは社内向けポッドキャスト「沼ラジオ」を開始。既に40回を超える配信を行っています。
更に2024年5月には社外向けにも配信を開始。配信プラットフォームには主要なポッドキャスト配信サービスを採用。「例えば営業の人が車の運転しながら聴いても心地いいように、普通のラジオのような音質を目指しました」と森久氏は説明します。音質へのこだわりは、可能な限り多くの社員に届けたいという思いの表れです。
コミュニティの運営基盤としては、Office 365のTeamsを活用。大きなTRIBUSコミュニティの中にいくつかのチャンネルを設け、TRIBUSの事務局のお知らせチャンネルに加えて、「このようなことを手伝ってほしい」「このようなことを知っている人募集」といったチャンネルを用意しています。

TRIBUS沼ラジオは、株式会社リコーのスタートアップ企業や社内外の起業家の成長を支援して事業共創を目指す統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS(トライバス) 」の事務局が運営するポッドキャストです。TRIBUS沼ラジオでは、新たな価値創造に挑戦するスタートアップや社内起業家、TRIBUSに関わる仲間達をゲストに迎え、さまざまなエピソードを深掘りしていきます。
リスナーの皆さんをTRIBUSの沼に頭のてっぺんまで浸かってもらうことをミッションに、聞けば聞くほどハマる、そんな魅力的なコンテンツをお届けします。
ぜひ、TRIBUSポッドキャストをフォローして、最新エピソードをお楽しみください。通勤時間やリラックスタイムに、ちょっとした刺激と発見をお届けします。
各Podcast配信プラットフォーム
■Spotify
■Amazon Music
https://music.amazon.co.jp/podcasts/ce141c82-7424-4637-9b56-9df2ae17932f/tribus
■Stand.FM
https://stand.fm/channels/665441fd316143a771e8fbaf
■Apple Podcast
https://podcasts.apple.com/us/podcast/tribus/id1748712702
■Youtube Music
https://www.youtube.com/channel/UCIp0DXXmeRTY_wMKS7KBHWQ
自発的な広がりを生むメカニズム
現在、TRIBUSコミュニティは事務局からの一方的な情報発信の場ではなく、メンバー同士が活発に情報交換を行う場となっています。「このようなヒアリングをしたいのだが協力してくれる人いませんか」という要望や、「このようなセミナーを外でやっているよ」といった情報共有が自然に行われています。
「事務局がメインで投稿するのではなく、自然に上がってきた声を活かしています」と森久氏は語ります。その成果は、プログラムへの応募数の増加にも表れています。2024年の応募はここ数年では最多を記録。「なぜ上がってきたのかにつながるきれいな施策があったわけではありません。何か大きな変化点があったわけではないのですが、これまでの挑戦者の促成が知れ渡るに伴い着実に上がってきています」と森久氏は分析します。

リコーの企業文化との共鳴
TRIBUSの成功の背景には、リコーの企業文化も影響しています。「他の人を手伝うということが好きな傾向がある」と森久氏は指摘します。この文化がコミュニティやサポーター制度と共鳴し、多くの社員の参加を促進しているのです。
また、創業者の言葉に込められた価値観が、現在の社員にも受け継がれていると森久氏は感じています。「共通の価値観として以前からあるものとして、大体の社員なども持っているからそれが当たり前なのかな」と語りました。
継続的な進化の秘訣
プログラムの運営において、森久氏が大切にしているのは小さな改善の積み重ねです。
「そのときそのときに参加している人とか、関わるステークホルダーが何に困っているのか、何を必要としているのかということを、小さいことでも、プログラムに少しずつ入れてチューニングを重ね続けています」(森久氏)
先日実施された「卒業式」では、過去5年間の軌跡を1,000人以上の社員と共有。「自分でも行けるかも」「やってみたい」という新たな参加意欲を喚起することにも成功しています。
大企業における新規事業創出の難しさが指摘される中、TRIBUSは着実に成果を上げ続けています。その成功の鍵は、「熱くない」視点を大切にしながら、誰もが参加できる仕組みを丁寧に作り上げてきたことにあります。そして、そのアプローチは確実に組織を変えつつあるのです。
森久さん、貴重なお話をお伺いさせていただき、ありがとうございました!
関連記事|リコーが仕掛けた新規事業創造の実験とは?
社内外からイノベーターを募り、リコーのリソースを活用しイノベーションにつなげるプロジェクト「TRIBUS」。
社内からの新規事業創出と外部スタートアップとの協業。一見すると異なるベクトルを持つ2つの取り組みを、なぜ同時に進めようと考えたのでしょうか。
リコー TRIBUS推進室 TRIBUSプログラム運営事務局 森久 泰二郎氏にお話を伺いました。
リコーが仕掛けた新規事業創造の実験——社内起業と外部スタートアップの共創プログラム







