
北陸発、エネルギー×スタートアップの共創プログラム——NGAS-Accelerator Program 2024で5社が成果発表

日本海ガス絆ホールディングスグループは昨年12月18日、オーバード・ホール中ホール(富山市)にて「NGAS-Accelerator Program 2024」の成果発表会を開催しました。このプログラムは、北陸地域への新しい価値提供を目指し、55社の応募の中から選ばれた5社のスタートアップ企業と、同社グループの社員であるカタリストが約4カ月間にわたって取り組んだ共創活動の集大成です。
IoT見守りサービス、波力発電、バイオテクノロジーなど多岐にわたる分野で、エネルギー企業とスタートアップの連携による革新的なビジネスモデルの創出に挑戦した成果が発表されました。
採択企業5社(五十音順)
Yellow Duck株式会社( https://yellow-duck.jp/ )
登壇者:中山繁生
事業内容:カーボンニュートラル達成に向けた海洋再生可能エネルギーによる発電システムの開発
連携内容:富山県射水市の日本海にて初のポータブル波力発電装置の実証実施
株式会社otta( https://otta.co.jp/ )
登壇者:中谷元
事業内容:スマート見守りシティプラットフォーム
連携内容:行政や市内小学校、PTAなど複数のステークホルダーへのヒアリングを通じて、富山県エリアにおけるIoTを活用した地域参加型のタウンセキュリティの実現に向けた事業検証
環境微生物研究所株式会社( https://ybaba1.wixsite.com/rumen115 )
登壇者:馬場保徳
事業内容:平時も災害時にも資する自立運転可能なメタン発酵システム「エコスタンドアロン」の社会実装
連携内容:資源循環型社会づくりに取り組まれている地域企業やゴルフ場などにヒアリングを実施し、「エコスタンドアロン」の北陸地域への実装可能性の検証と共創モデルについて検討
株式会社きづなろ( https://qiznalo.com/ )
登壇者:大槻知史
事業内容:骨格データとAIによる転倒防止!北陸発エイジテックモデル“絆”ろうプラン
連携内容:ガス展2024ご来場者の方々に見守りサービス「きづなろセンシング」のコンセプトについてのアンケート調査実施、有料老人ホームやサ高住へのヒアリング等による事業検証
株式会社ヤモリ( https://www.yamori.co.jp/ )
登壇者:藤澤正太郎
事業内容:単身高齢者のIoT見守りサービス「みまもりヤモリ」
連携内容:日本海ガスの北陸エリアの不動産会社向けにIoTセンサーの見守りサービスを提供開始。また日本海ガスと共同で新会社を設立し、空き家を再生して賃貸物件として提供する事業を検討。
環境微生物研究所の挑戦

石川県立大学発のスタートアップ、環境微生物研究所の代表、馬場保徳氏は東日本大震災での被災経験から、「雑草からガスと電気を作る」という着想を得ました。同氏は牛の胃袋に住む微生物に着目し、12年の研究開発を経て、植物性廃棄物からメタンガスを生成する「エコスタンドアロン」の開発に成功しました。
このシステムは、牛の消化の仕組みを応用し、雑草や野菜くずなどの植物性廃棄物を微生物によって分解し、メタンガスを生成します。生成されたガスは都市ガスとして利用でき、発電機と組み合わせることで電気も供給可能です。現在、石川県内のショッピングセンターで実証実験を行っており、微生物の培養に成功すれば、一度の投入で継続的な発酵が可能になるという画期的な技術を実現しています。
日本海ガス絆HDグループとの協業では、ゴルフ場から排出される年間200トンの刈り草を活用した事業化を検討しました。試算では、年間約1万立方メートルのメタンガスが生成可能で、これは経産省が掲げる都市ガス事業者の目標として掲げる「カーボンニュートラルガス供給量の1%」に相当します。また、ゴルフ場にとっては、仮に年間200トン程度の刈り草が発生し、それらを費用をかけて廃棄物処理をした場合にかかる年間600万円の廃棄物処理費用が不要になるほか、発酵液を肥料として活用することで循環型の事業モデルを構築できます。
このような条件における事業の収支計画では、1億円の設備投資に対して年間最大1030万円の経費削減効果が見込まれ、補助金を活用した場合、4.9年での投資回収が可能と試算しています。市場規模については、国内全体で1兆7590億円、実際にアクセス可能な現実的な市場として550億円を見込んでいます。
今後のロードマップとして、2026年までに小型タイプの仕様を確定し、能登地方のスーパーマーケットでの実証を経て販売開始を目指します。すでに経済産業省と遠隔監視システムの実証を行っており、復興庁や福島イノベーションコースト構想とも連携して自動化の実証を進めています。2027年までには大型タイプの開発も計画しています。
さらに、カンボジアなど途上国への展開も検討しており、地雷除去後の農地活用プロジェクトとの連携も模索しています。現地では農家の資金不足によりガス・電気・肥料の調達が課題となっていますが、「エコスタンドアロン」の導入により、現地で入手可能な野菜くずや雑草からこれらを自給することが可能になります。現在、カンボジア農水省との協議やJICAへの予算請求を進めており、国際貢献の可能性も広がっています。
ヤモリの空き家再生事業

ヤモリは、空き家問題の解決とIoT見守りサービスを組み合わせた新しいビジネスモデルの構築に挑戦しています。同社の藤澤正太郎代表は「不動産の民主化」をミッションに掲げ、日本海ガス絆HDグループとの協業により、北陸地域での事業展開を開始しました。
共創プログラムでは、二つの取り組みを並行して進めました。一つは北陸エリアの不動産会社向けのIoT見守りサービスで、12月からすでにサービスを開始。もう一つは、日本海ガスとの合弁会社設立による空き家の賃貸化事業です。
空き家問題について藤澤代表は、「人もなし、物もない、金もない」という三重の課題があると指摘します。空き家バンクを設置している自治体のうち、4分の1以上で成約実績がゼロという現状があります。一方で、日本の中古住宅市場は米国の4分の1程度の規模があり、成長の余地は十分にあると分析しています。
同社の事業モデルは、古い空き家を買い取って内装をリフォームし、賃貸物件として運用するというものです。すでに東京・下赤塚では、「お化け屋敷」と呼ばれていた物件を学生向けシェアハウスとして再生した実績があります。物件の購入から運営管理までをAIでサポートするクラウドシステムを開発しており、3年弱で100億円以上の物件購入実績を上げています。
日本海ガス絆HDグループとの協業では「日本海ガス空き家賃貸株式会社(仮称)」の設立を計画しています。新会社では富山県内の約20件の空き家を再生することを目指しています。
日本海ガス絆HDグループとの連携のメリットとして、80年以上の実績に基づく地域との関係、ガス工事を通じた工務店ネットワーク、そして不動産会社との関係性強化が挙げられます。また、地域金融機関との連携も視野に入れており、地域活性化に資する事業として検討中です。
藤澤代表は「空き家は地域の価値を下げる大きな課題だが、長期目線で受け皿となる仕組みを作ることで、新たな価値を生み出せる」と将来への展望を語っています。
きづなろのAI見守りサービス
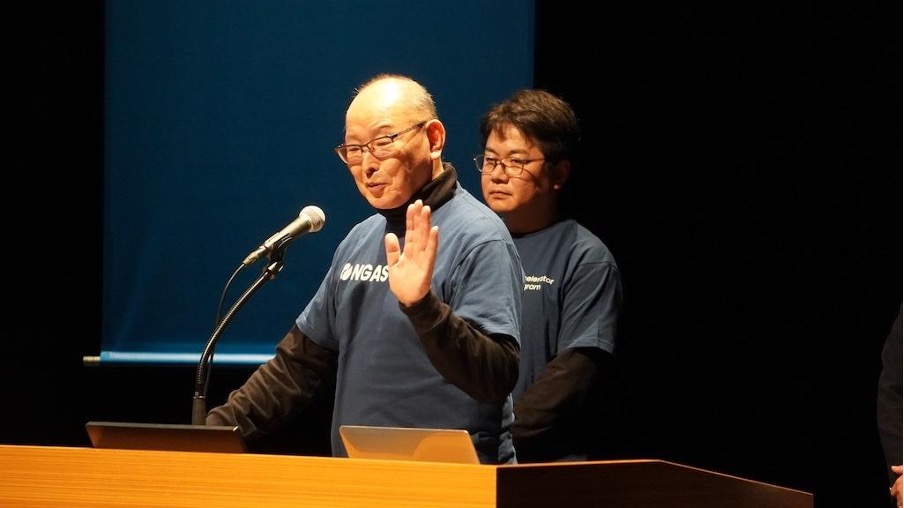
きづなろは、AIによる骨格推論技術を活用した転倒検知システムで、高齢者見守りの課題解決に取り組んでいます。大槻知史代表が自身の母親の転倒事故をきっかけに開発を始めたこのシステムは、既存の見守りサービスでは対応できなかった課題を解決する可能性を秘めています。
同社のシステムの最大の特徴は、AIによる骨格推論技術を用いた転倒検知です。従来の見守りサービスでは、体の傾きや頭の高さなどの単純な指標で転倒を判断していたため、正面からの転倒や距離による誤検知などの問題がありました。一方、このシステムは関節位置の情報のみを取り出し、AIが人の手を介さずに独自に転倒を判定できる仕組みを実現しています。
プライバシーへの配慮も特筆すべき点です。日本海ガス絆HDグループが実施したガス展でのアンケート調査では、「見られている感」が見守りサービス導入の障壁となっていることが判明。きづなろのシステムは「ピンピンセンサー」と呼ばれる技術により、骨格の関節位置情報のみを取り出すため、万一ハッキングされてもプライバシーを守れる仕組みとなっています。
さらに、このシステムは転倒検知だけでなく、健康状態の予防的な把握も可能です。歩幅の変化や方向転換時のふらつきなどを継続的に記録・分析することで、パーキンソン病やロコモティブシンドロームの早期発見に役立てることができます。また、記録機能により、救急搬送時の発症時刻の特定など、医療機関への正確な情報提供も可能になります。
高齢者介護事業者へのインタビューでは、夜間の3回の安否確認がスタッフの大きな負担となっていることや、マットセンサーなどの既存技術では限界があることが明らかになりました。実際の施設での1ヶ月の試験運用では、スタッフの心理的負担の大幅な軽減効果が確認されています。
技術面では現在、複数人が存在する場合のトラッキングシステムの改善など、いくつかの課題に取り組んでいます。これらの改善を重ね、サービスローンチを目指しています。
事業展開については、実証を通じてビジネスモデルを確立し、その後、全国展開、さらには世界展開を視野に入れています。すでにドイツやフィンランドのケアプロバイダーからも引き合いがあるといいます。
大槻代表は「お家が健康診断するヘルスケアエコシステムを北陸から始めたい」と意気込みを語ります。日本海ガス絆HDグループとの協業により、見守りサービスを通じて新たな顧客接点を創出し、地域の安心・安全に貢献することを目指しています。
イエローダックの波力発電への挑戦

イエローダックは、海のエネルギーを活用した新しい電力供給の可能性を追求しています。同社の中山繁生代表は、再生可能エネルギーの適地が減少する中、海洋エネルギーの可能性に着目。波の力は風力の5倍、太陽光の20倍のエネルギー密度を持つという特性を活かし、独自の波力発電装置の開発に成功しました。
同社が開発したのは、設置から2時間で発電可能になるポータブル波力発電装置です。従来の海洋発電は大規模な工事が必要でしたが、この装置は持ち運びと設置が容易なのが特徴です。波の上下動を利用して約300キロの装置を動かし、そのエネルギーを電力に変換する仕組みを採用しています。
実証実験までの道のりは困難の連続でした。海での実証には漁業者、港湾管理者、海上保安庁、場合によっては国交省まで、多くの関係者の承認が必要です。日本海ガス絆HDグループのカタリストチームは、車でのアクセスが可能で護岸が整備された理想的な実験場所を求めて北陸各地を走り回りました。
転機は11月6日に訪れます。富山県土木部富山新港管理局との相談により、伏木富山港新湊地区の南水路での実証実験が可能になったのです。急ピッチで許可申請を進め、11月22日に許可を取得。運送業者20社以上に断られる中、「新しいことをやるなら協力する」という1社の協力を得て、12月10日に装置を搬入することができました。
実証実験では四つの評価項目を設定。設置の容易さ、安全性、波への追従性、太陽光発電との比較を検証しました。湾の奥という波が穏やかな不利な条件下でも、約0.1メートルの波により実証実験中に141ワットアワーの発電量を達成。これはスマートフォン10台分の充電に相当します。また、同条件下での発電時間を比較すると、太陽光の15分、風力の60分に対し、波力は612分と圧倒的な優位性を示しました。
今後の展開として、離島でのディーゼル発電の代替を第一段階に位置付けています。次いで港湾設備での活用を目指し、最終的には船舶に搭載して発電する構想も描いています。中山代表は「日本の海域は陸地の12倍あり、そこに眠るポテンシャルを引き出したい」と意欲を見せます。
実証実験の最終日、装置の撤収時に虹がかかったといいます。「新しい再生可能エネルギーの扉が開いた」と捉える中山代表。北陸から革新的なエネルギービジネスが生まれる可能性を示唆する象徴的な出来事となりました。
ottaの地域セキュリティ構想

ottaは、IoTを活用した地域参加型のタウンセキュリティプラットフォームの構築に取り組んでいます。福岡に本社を置く同社は、創業から10年で全国39エリア、15万人以上の利用者を抱えるまでに成長。しかし、北陸エリアでは新潟県・新潟市と石川県羽咋市での展開にとどまっており、富山での事業展開を目指しています。
同社のサービスの特徴は、小型のビーコン端末を活用した見守りシステムです。希望する児童に無償で配布される守り型の端末には、位置情報を発信するビーコンが内蔵されています。学校の校門や下駄箱付近に設置された基地局が、児童の登下校時刻を自動的に記録します。また、通学路沿いの店舗、病院、公共施設にも基地局を設置し、さらにIoT機器を搭載したタクシーによる「見守りタクシー」も運用することで、地域全体での見守り体制を構築しています。
このシステムは子どもの見守りだけでなく、高齢者向けのサービスも展開しています。端末を杖や靴に装着することで、認知症の方の行方不明時の早期発見に役立てることができます。
富山市での展開に向けて、同社は市内小学校の保護者を対象にアンケート調査を実施しました。その結果、68%の家庭で子どもだけでの留守番があり、80%の保護者が「子どもの居場所を知りたいと思ったことがある」と回答。見守りサービスの認知度は42%にとどまるものの、72%が「サービスを利用してみたい」と回答するなど、高いニーズが確認されました。
最近の技術革新として、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT®」 との連携も実現。全国4万台のチャージスポットに見守り機能が追加され、富山でも約110カ所での展開が予定されています。これにより、学校や通学路だけでなく、より広範囲での見守りが可能になります。
市場規模の試算では、富山市の児童数約1万8000人のうち、25%程度の約4500人の利用を想定。富山県全体では児童数約4万5000人の25%にあたる1万1250人の利用を3〜7年かけて目指す計画です。また、高齢者向けサービスについては、65歳以上の単身世帯(富山市内約2万世帯)の10%、約2000世帯の利用者の獲得を目指します。
日本海ガス絆HDグループとの協業により、同社は地域インフラ企業としての信頼性を活かした展開を目指します。各ステークホルダーからは前向きな反応を得ており、地域特性を考慮した実証実験の実施を検討中です。また、ガス事業者としての顧客基盤を超えた新たな接点を創出し、IT技術を活用した地域・社会課題の解決に貢献することを目指しています。
新たな価値創造への期待

「掛け合わせのなせる技」——。日本海ガス絆ホールディングス・新田洋太朗社長は、今回のプログラムを通じて生まれた成果をこう評価します。同社グループが持つ約80年の地域インフラ事業の経験と、スタートアップ企業が持つ革新的な技術やビジネスモデルの掛け合わせにより、これまでにない新しい価値が創出されつつあります。
各社の取り組みは、カーボンニュートラル、暮らしの安全、空き家問題など、地域が直面するさまざまな課題に応えるものとなりました。
「当社グループでは2030年までの中期ビジョンとして『ネクストビジョン』を掲げています」と新田社長は語ります。
「ガスエネルギーにとどまらない、様々な事業にチャレンジをして地域のお客様の役に立つこと、そして社員の活躍の場を広げていくこと。本日の発表と実証を踏まえ、一つでも多く事業化を実現し、より地域の役に立てる企業グループになっていきたい」(新田社長)
日本海ガス絆ホールディングスグループの平田純一副社長も「中小の都市が直面する空き家問題や、新しい再生可能エネルギーの供給、安心インフラの整備など、今回のプログラムで生まれた成果は、まさに地方創生のモデルケースとなり得る」と期待を寄せています。
このプログラムを通じて、北陸という地域特性を活かしながら、エネルギー企業とスタートアップ企業の協業による新しいイノベーションの形が見えてきました。
実証実験から事業化、そして地域課題の解決へ ——。北陸発の新しい価値創造への挑戦は、まさにこれからが本番を迎えます。







